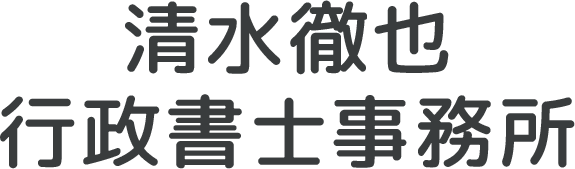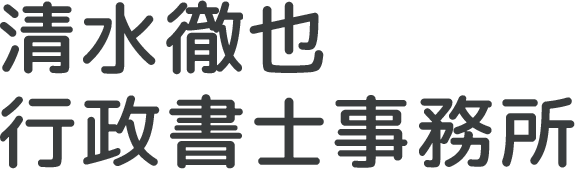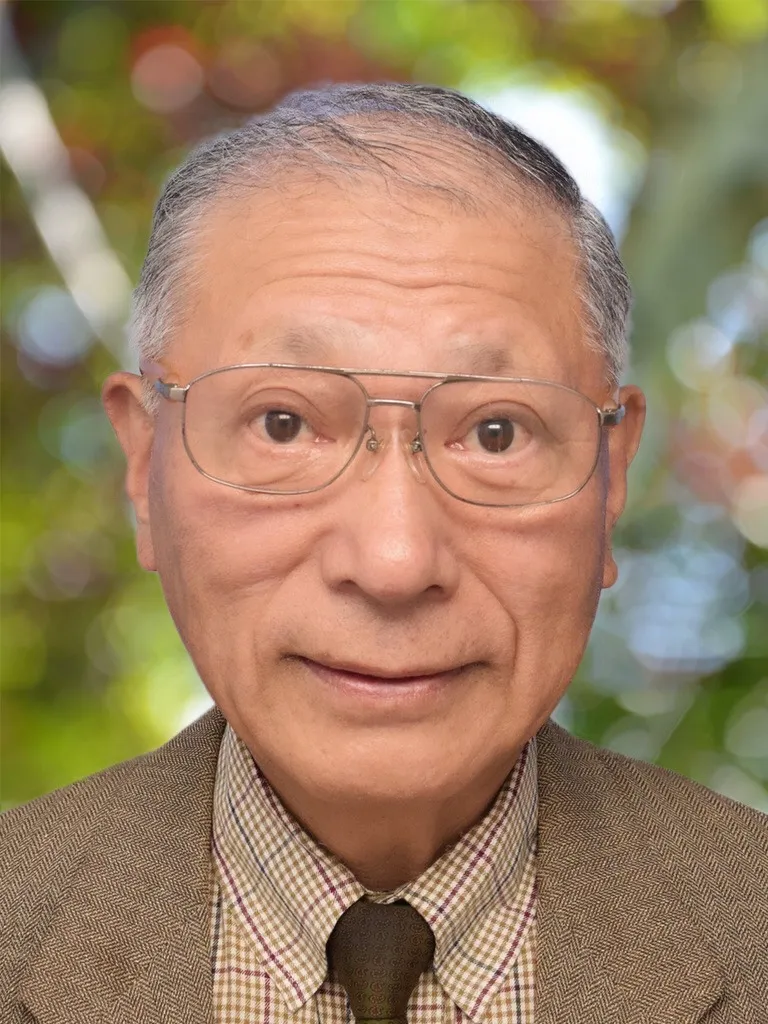法的効力のある遺言を作成するためには
WILL
遺言書は、故人の意思を明確に示すための重要な文書です。
そもそも遺言と相続はどのような関係にあるのでしょうか?
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。
一方相続とは、亡くなった方の財産上の権利義務を承継することです。
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった者が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、残念なことはありません。
遺言は、そうした問題を軽減し、防ぐため、遺言者自らが財産のどうするかを決め、相続をめぐる争いを防止しようとするために非常に有用な働きをします。
しかし、その内容によっては、財産が分与されることを期待をしている親族との間で争いが生じてしまいます。
そもそも形式が適切でないと遺言としての法的な効力が認めらません。
遺言は相続を円滑に行うための大変有用な手段ですが、遺言者の意思が書いてあれば良いというものではありません。
有効な遺言を作成し、争いを防ぐためには、専門家のサポートが不可欠です。
地域密着型の当所では、相談はすべて無料で行なっています。
こちらにおいで頂かなくても、ご自宅やお近くのカフェなどでお話しをお伺いしています。
知り得た個人的な情報は固く守ります。
遺言関係業務
※消費税、実費は別になります
|
遺言関係業務 |
内容 | 料金 |
|
自筆遺言の保管制度活用のサポート |
40,000円 |
|
| 自筆遺言の作成サポート | 30,000円 | |
|
公正証書遺言の作成サポート |
50,000円 |
遺言と相続の関係は、遺言が法定相続に優先する、という原則に基づいています。遺言書を作成することで、法定相続分よりも優先して財産の承継先を決めることができます。
民法上相続人に含まれない人(内縁関係の人、血縁関係にない人や団体など)に遺産を分配することができます。
遺言書があれば、遺産分割協議を省略でき、相続手続きを簡略化できます。
遺言書が残されていたとしても、相続人全員の合意が取れれば遺言の内容とは異なる分配内容にすることができます。ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害する場合は、遺留分権利者の減殺請求に応じなければなりません。
遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合には、刑事罰を受けるほか相続権を失う結果となってしまうので要注意です。
遺言書が残されていたとしても、相続人全員の合意が取れれば遺言の内容とは異なる分配内容にすることもできます。
【自筆証書遺言書保管制度】
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が法務局に自筆で作成した遺言書を保管してもらう制度です。
2020年7月10日より開始されました。
メリットデメリットをご紹介しますが、この制度は3900円で出来る公的な保管制度で、家庭裁判所の検認も入りませんので、デメリットの部分をよく把握しておけば大変有用な仕組みです。
【メリット】
遺言書の紛失や盗難、改ざんを防ぐことができる
家庭裁判所の検認手続きが不要になるため、相続手続がスムーズになる
法務局職員が保管の際に形式要件を確認するため、無効となる可能性が低い
相続人(あらかじめ指定した方)に遺言を保管していることを通知してくれる
【デメリット】
保管申請手数料や閲覧等の手数料がかかる
遺言者本人が法務局に出頭しなければならず、代理人は手続きができない 付き添いは可
法務局では遺言の内容については審査されないので、遺言の内容に法的な問題を含んだ遺言が作られてしまう危険性がある
【手続き】
最寄りの窓口で管轄や遺言書保管所一覧を確認する
予約や手数料の準備を行う
遺言書原本及び画像データとして適切に長期間保管される
適切な遺言作成でトラブルを予防
遺言書には、財産分配や相続人の指定など、さまざまな内容を含みますがこれらを明確に記載することで後々のトラブルを防ぎます。遺言を作成する際は、遺言者の意思を尊重しながら家族間の円満な関係を維持できるよう心がけます。また、遺言の作成だけでなく相続手続きのサポートも行い、相続財産の調査や遺産分配の調停など、相続に関するさまざまな問題にも桐生市で対応いたします。相談者様のご要望に合わせて適切な解決策を提案し、円滑な相続手続きを実現いたします。